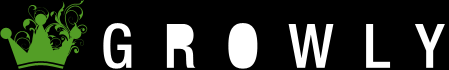2013.02.23(Sat) bed presents "turn it off~ヤング・ゼネレーション~"
『ヤング・ゼネレーション』。自転車レースに青春を賭ける若者たちと家族の交流を描いた、青春映画の王道とも言える1979年のアメリカ映画だ。青春映画なんて言うと、青いしダサいし、なんだかこそばゆい。いつの間かそんなふうに感じるようになってしまっていた。自分でも気付かないふりで、随分と年を取ってしまったのかもしれない……なんて思っていたけれど。そんな青春映画と同じタイトルを冠したこの日のライヴに、そんな錯覚はふっ飛ばされた。
トップバッターはピアノガール。京都の若手の中でも名実ともに頭ひとつ抜きんでた、今後京都の音楽シーンを牽引していくであろうこと間違いないバンド――なんて言うと大袈裟に聞えるかもしれないけれど、そこら中に蔓延する、どこにでもいるようなバンドと彼らの何が違うか、結局は覚悟の問題なんだろう。彼らのステージを見れば、それは一目瞭然。この日もヴォーカルの内田が言い放った、ステージに立つ時はいつも死ぬ覚悟だという言葉に嘘はなく、名立たる先輩バンドのステージを前に、先輩も後輩も知ったことかと、お前ら全員こっち見ろと、食いちぎらんばかりの勢いで挑みかかってくる。本気で来られたら、こちらだって真っ向から受けて立つしかない。食うか食われるかの攻防にも感じられるけれど、そんなやり取りの中で着実に彼らの音楽が浸透しているのがフロアの様子から伝わってくる。人に届ける時に何が一番必要なのか、彼らは先天的に知っているのだと思う。「すべての17才のために唄います」、そう告げて鳴らされた「17才」。潤んだ瞳でステージを見上げる少女や、彼らと同世代であろう少年たちがフロアで一緒になって唄っている姿が、とてもとても眩しいものに感じられた。

続くLOSTAGE。本気で挑んでくるならこちらも本気を出すだけ、とでも言いたげな、張り倒されそうなほどの爆音。陰りも光も諦念も希望も、なにもかもぐちゃぐちゃにしてくれる。そうなんだ、僕らがロックミュージックに求めるのはこれなんだ。音の塊が、鼓膜に、体に、叩きつけられるのを感じながら改めてそう思う。退屈な日常を巻き込んで、飲み込んで、ぶん回して、火を放って。欺瞞や偽善が満ち溢れたつまんない世界をぶっ壊してくれなきゃ嘘なんだ。最新アルバム『ECHOES』からの楽曲を中心に構成されたセットリストの中、「僕の忘れた言葉たち」や「BLUE」など、一聴すればポップに思える楽曲も、ライブで体感するとことさらに、根底に脈々とマグマのような熱が流れているのが感じられる。その熱で、荒ぶる音で、くだらないものをぶった切り、ロックミュージックのスピリットをまざまざと見せつけてくれるLOSTAGEというバンドは、今では随分と数少なくなってしまった、信頼に値するロックバンドであると思う。途中、機材トラブルに見舞われたりもしたけれど、それでもただただひたすらに、フロアを、そして恐らく共演であった2バンドすらも圧倒し、その存在感を、空間を共有していたすべてのものに刻みつけていった。


トリを飾ったのはこの日の主催者でもあるbed。さっきまでステージに渦巻いていた熱をスッと一変させ、どことなく寂寥感を灯した声とメロディが、激しくたぎっていた炎を鎮めるかのようにひたひたと沁みこんできた。決して熱を持たないわけではないそれは、例えるなら蝋燭の芯を燃やすあの青白い火のようで、不器用に感じるくらいに実直な歌にも力強さを与えている。彼らの響かせる情景にぐっと引き寄せられていく観客に混じり、フロアには彼らを愛してやまない仲間たちの姿も増えてくる。愛情込みの野次も、それに笑って応える姿も、その光景を見るだけでもう、彼らが歩んできたここまでの道のりが透けて見えるような気持ちになった。〈明日は今日より少し前に進もう〉という「ねがいごと」の一節のように、ひとつひとつ積み上げて進んできた彼らだからこその、今日のこの日の企画であったと思う。ここに至る経緯を、MCでは少し茶化して語っていたけれど、お互いを認め合い、切磋琢磨し戦える盟友を持てるのも、彼らが自分自身と音楽に誠実にあるからだろう。音が鳴ってる瞬間を目の前にそんなことを考えるのは余計なのかもしれない。けれど、ついついそんな無粋なことをしてしまうくらい、この日のbedのライブは胸に温かかった。

青春の青さなんていつまでだって、それを信じて追い続ける者たちの傍らにあって、時に眩しく、時に荒々しく、そして時にしんしんと胸に積もるものなんだ。知らぬ間に終わらせていた気になっていたけど、そうじゃない。僕らが望む限り、僕たちの青春は終わることなく続いていく。そんなことを教えられた気がした夜だった。
(文・写真:新井葉子)